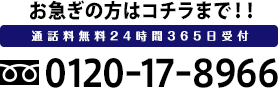六月三日深夜。兄からの電話。「今、お母さん死んじゃったよ・・・」私は、「わかった」としか答えることが出来なかった。コロナの影響で入院後は約四年会えなく、看護師に繋いでもらったテレビ電話の会話や入院前に話した事など・・・実家へと向かう移動中の飛行機や電車の中で母との沢山の思い出が浮かんでくる。
自宅に着くと顔に白布が被せられた母が寝ていた。四年ぶりの対面は一言も話しをしてくれない色白い顔の母だった。私はすぐさま母が愛用していた化粧品を探し出し娘と一緒に化粧を施した。これで「綺麗になったよ!お母さん・・・」と話しかけた瞬間、「俊巳ありがとう」と笑みを浮かべる母の顔が浮かんだ。すると娘が「おばあちゃんは派手だったから」と仕上げにハイライトを入れてくれた。娘には娘なりの祖母への思いがあったのだろう。それから、母を囲み兄夫婦と全員で昔懐かしのアルバムを見ながら思い出を振り返った。
通夜当日、納棺の時間に葬儀社が自宅へやってきた。葬儀は、その地域で慣習が異なる。私の地元北海道では、映画「おくりびと」のように納棺師が旅支度を綺麗に整えてくれ、家族はその光景を眺めているだけ。でも、どうしても母に自らの手で旅支度をしたいと思い、娘と息子と一緒にピンク色の手甲・脚半・足袋を着け身支度を整えさせてもらった。
式場に移動し遺影写真に目を向けると、遺影写真前には赤とピンクの大きなアンスリウムがたくさん生けられていた。母の日にカーネーションではなく、母の好きなアンスリウムを贈っていたことを葬儀社に伝え、祭壇にも使ってもらうようにお願いしていた。花に囲まれた遺影写真を眺めていると、子供の頃のように私と兄に呼びかけてくれそうな、そんな優しい笑顔だった。
私はこれまで葬儀者として、たくさんのご家族のお見送りをお手伝いしてきた。私なりにご遺族に寄り添い、ご要望を伺い満足のいく葬儀を行なっていただけるよう心を尽くしてきた。それでも、今回自分の母を送る立場となり一つの目線が明確になった。人一人を送るということは、家族、親戚、兄妹など、たくさんの人の思いを汲み取り一つの葬儀を作り出していく難しさを、今まで頭では理解していたつもりだったが母を送り出したことでより実感として心に刻むことができた。
これからも人を送るという仕事を生業としている者として、できる限りの精進を尽くして行こうと思った。合掌
文責:佐々木俊巳